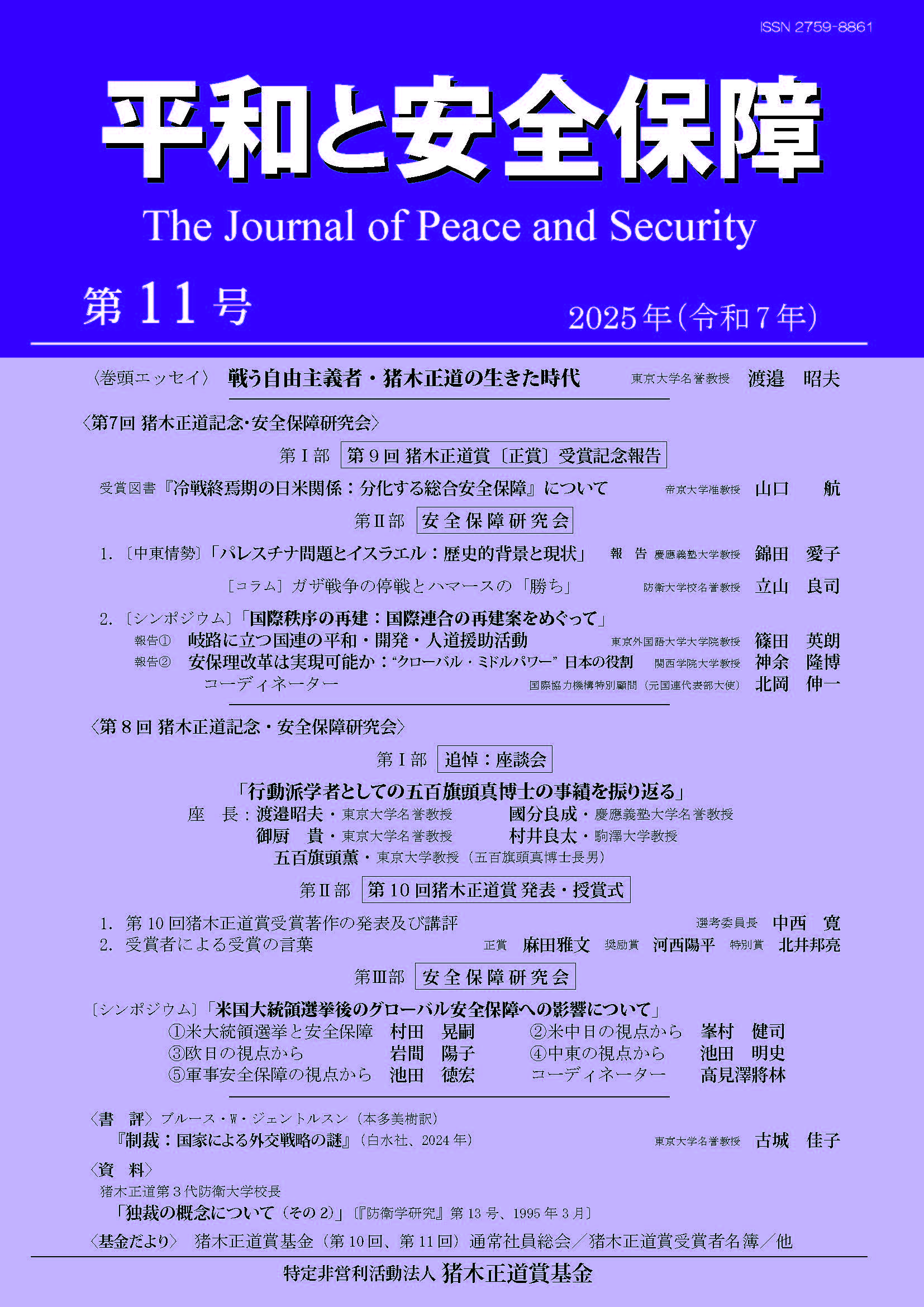|
第9回「猪木正道記念・安全保障研究会」の概要報告 特定非営利活等法人猪木正道賞基金では、令和7年6月22日(日)国際文化会館・講堂において、(第9回猪木正道記念・安全保障研究会を開催しました。 国際文化会館 本館
本研究会の第Ⅰ部【戦後80年:記念報告】1では、渡邉昭夫東京大学名誉教授による「日米同盟と日本外交の80年」の報告及び安藤優香慶應義塾大学日印研究ラボ上席研究員による質問があり、2では、永澤勲雄猪木正道賞基金理事による「『昭和天皇拝謁記』に見る昭和天皇の軍備・安全保障観と吉田茂首相の安全保障構想―その相違と一致点―」の報告が行われました。 第Ⅱ部【特別企画:シンポジウム】では、「急変する世界秩序の中で日本の安全保障を考える」をテーマに、田中 均日本総研国際戦略研究所特別顧問による〔基調講演〕が行われ、これを受け、徳地秀士平和・安全保障研究所理事長を座長に、パネリストに梅本哲也静岡県立大学名誉教授、神谷万丈国際安全保障学会会長、植木千可子早稲田大学教授、北井邦亮時事通信社外信部編集委員が参加して〔パネル・ディスカッション〕を実施しました。 (第9回)猪木正道記念・安全保障研究会の写真による概要は以下の通りです。
〈研究会の概要〉 開 会 総合司会 米田富太郎事務局企画委員
第Ⅰ部【戦後80年:記念報告】 1. 日米同盟と日本外交の80年 報告者:渡邉 昭夫(東京大学名誉教授・青山学院大学名誉教授)
本研究会の渡邉昭夫東京大学名誉教授による「日米同盟と日本外交の80年」の報告は、三つの難問として、1) マッカーサー、2) 天皇、3) 原爆を取り上げ、とりあえずの答えとして、1) キリスト教化、2) 人間宣言、3) 原爆裁判からエマヌエル・トッド争論まで― 若いころの若泉(敬)について、考えを述べ、広島、長崎の原爆投下が戦後日米関係の始まりとなったとの認識を表明され、第二次大戦の戦犯者は、日本のみでなく日米双方に存在するとの見解を示しました。そして、最近のトランプ政権の言動から明らかなように、戦争は力のアンバランスにより惹起されることから、戦争抑止のために日本も相応に防衛力を増強することが必要であると主張し、報告を終えました。
報告者 渡邉昭夫先生への質問
質問者:安藤 優香(慶應義塾大学日印研究ラボ上席所員)
引き続き、安藤優香慶応義塾大学日印研究ラボ上席研究員から、戦後80年間における、石油危機や繊維問題、日本による国連改革問題、さらに今回の米国の対イラン攻撃に見る米国の抑止の有効性等の4つの問題が提起され、両者間で活発な質疑応答が行われました。
渡邉昭夫名誉教授によるこれまでの研究の集大成ともいうべき報告のため渡邉昭夫ゼミOB多数の参加があり、本報告は大変活発にかつ盛況のうちに実施されました。
会場(講堂)風景
2.「『昭和天皇拝謁記』に見る昭和天皇の軍備・安全保障観と 吉田茂首相の安全保障構想 ―その相違と一致点について―」 報告者 永澤 勲雄(特定非営利活動法人猪木正道賞基金理事)
令和3年から5年にかけて岩波書店から刊行された『昭和天皇拝謁記 ―初代宮内庁長官田島道治の記録―』(全7巻)によつて、これまで表に出されてこなかった昭和天皇の戦争観、歴史認識及び民主主義や共産主義に対する見方、そして安全保障観について、田島長官による克明な記録によって明らかになった。次の永澤勲雄理事による報告は、この『拝謁記』の中から、特に昭和天皇の敗戦後の日本の軍備・安全保障観を取り上げ、時の吉田茂首相の安全保障観構想との相違と一致点について、外交資料等貴重な資料に基づき報告を行った。
第Ⅱ部【特別企画:シンポジウム】 テーマ「急変する世界秩序の中で日本の安全保障を考える」
〔基調講演〕 過度な対米依存を脱し多様な枠組構築へ 講演者:田中 均(日本総研国際戦略研究所特別顧問・元外務審議官)
田中特別顧問は冒頭、「国際秩序の変化、これにどう臨んでいくかについて私の意見を述べたい」と発言し、1. 世界秩序の変化、2. 日本の在るべき安全保障体制、の二つの課題について話を進められた。1.では、「リベラルな国際秩序」の変貌 として ①米国は「世界の警察官」の役割の放棄、②国際主義が希薄に~国連・WTO・G7機能の低下、他。2.では、まず、トランプのアメリカにどう向き合う?として、長期的には憲法改正・安保条約改正・核保有(現状では選択肢ではない)に関して意見を述べ。次に、安保堅持と外交多角化 として ①米国への過度の依存は日本の国益ではない~トランプ的アメリカがどこまで続くかは別として過剰な対米依存は米国に「当然視」され、外交自立性を奪う。②安保の三つの側面の拡充~安保能力拡充、信頼醸成枠組みの構築、安保環境をよくする外交、③CPTPPを軸とした「自由貿易ネットワーク」構築と地政学的能動外交の必要性を主張し、講演を終えました。引き続きフロアと活発な質疑応答が交わされました。
【パネル・ディスカッション】 座 長徳地秀士氏 パネリスト梅本哲也氏 パネリスト神谷万丈氏 パネリスト植木千可子氏 パネリスト北井邦亮氏
「急変する世界秩序の中で日本の安全保障を考える」
パネル・ディスカッカション開始にあたり徳地秀士座長は、4名のパネリストを紹介し、各先生方からは詳細なレジュメを用意されているので、時間の関係もあり、最初にそれぞれパネリスト報告をしていただき、その後ディスカッカションに入りたいと発言し、開始した。
第一パネリストの梅本哲也氏は、まず論点として「トランプ政権、国際秩序、日本外交―いくつかの論点―」を挙げ、①トランプ政権については、主権主義(sovereigntism)、これが一番妥当ではないかと指摘し、次に世界的な優越の維持が困難な場合における優先順位の選択について、restrainers(国内・西半球優先)、prioritizers(中国優先)、primacists(世界優先)が考えられるが、当面はprimacistsが維持されると話された。②国際秩序については、米国のリベラル国際秩序については、外からと内からの挑戦にさらされていると分析。③日本の外交は、現在、リベラル国際秩序の主要な支え手として評価を受けており、「経済にしろ、安保にしろ、現状を所与のものとせず、米国から突き放されるリスクへの対応も視野に入れた、より自律性の高い戦略を模索する必要がある」と主張し報告を結んだ。
第二パネリストの神谷万丈氏は、論点として「トランプ2.0が日本の安全保障に突き付ける試練」を取り上げ、①外交でも取引を重視、ル-ルに基づく国際秩序の維持が国益上重要という意識がないこと。米国が望むような形で外交・安全保障政策を展開するためには同盟国や同志国との協力が不可欠だとの認識が乏しく、同盟国との関係にさえ取引の視点を持ち込みやすいことを指摘。②米国による関税の一方的引き上げが、WTOのルールに違反するのではないかとの声に、トランプ政権は配慮を見せない。これは、これまでルールに基づく国際秩序を守ろうとする勢力のリーダーだった米国が、力任せに国益を追う国になってしまったことを意味する。③これは、ルールに基づく秩序を守るという日本の最優先の国益対する「国難」の本質であり、一層の危機を迎えているとの認識を示され、話を終えられた。
第三パネリストの植木千可子氏は、「1. 世界秩序はどう変化しているのか? 2. 日本の安全保障への影響、3. 日本はどうするべきか」の三つの点から考えを論じました。1. については、衰退する覇権国のあがきと秩序崩壊(覇権戦争)の危機について言及、トランプⅡ政権の戦略として、コストを他国に負担させる戦略縮小によって覇権維持を模索し、秩序維持を戦略目標としていないと発言。2. 安全保障への影響については、地域の緊張、不安定化は増加し、同盟国間の信頼性の低下をもたらすと指摘。3. 日本は、米国が戻ってくると期待し、NATOや地域諸国との連携強化・外交連携の必要を強調。まとめとして、米国の戦略的縮小は今後も続くと思うが、日米同盟を維持しつつ、米国依存から地域連携と独自防衛力増強に比重を移す。自由貿易体制は不可欠なので、日本が旗振りをし、長時間かけて集団秩序維持体制へ移行すべきと主張し、報告を終えました。
第四パネリストの北井邦亮氏は、「ポスト吉田路線の外交・安全保障政策」を論点に、長期的観点から日本のリアルな国防政策について発言しています。安全保障は、領土や国民の安全を守るだけでなく、「価値の体系」の共有を含み、他者に奪われる危険を低減することを基本とすると述べた。しかし、トランプ2.0が、内向き志向、取引主義により、リベラル国際秩序に背を向けることになれば、日米同盟の基盤は揺れることになる。日本は、これまで日米安保体制を基軸としつつ、自助努力強調(ポスト吉田路線)―平和安全法制(2015年)、戦略三文書改定(2022年)路線を推進してきたが、これからは現実主義の国防政策として、軍事的合理性の視点から、米軍との連携強化と自主防衛の「仕分け」を行い、日米の矛・盾という役割分担の再定義を行うことが必要と主張。最後に、核共有について、日本は核レイテンシー(遅延時間)による抑止力を考えることを問題提起し、報告を終えた。
以上の4名のパネリスト報告の後、徳地秀士座長は、ディスカッションに入る前に、先程の基調講演で田中均元外務審議官が長期的課題として問題提起した、憲法改正・安保条約改正・核保有について、皆さんはどのように思われているか質問されました。 ・梅本哲也氏は、憲法については解釈が曖昧なところがあるので、憲法のよい条文ができれば賛成です。安保条約についても現在の在り方がいびつなものであるにも関わらす、専門家の皆さんは世界秩序の大変換だと言われながら、旧来の枠内でそれを守ろうとするのかよくわからない。核の問題についてもオープンに議論をすべきだとの意見を述べられた。 ・神谷万丈氏は、日本人は戦後、「危険だけども、軍事力は平和のために役立つのだ」という認識が無くなったというところに問題があると思っている。憲法改正もそこに帰着するのであって、ウクライナ問題を見ても分かるように、その認識を変える必要がある。核の問題については、核装備は日本にとってプラスにならないと思っており、核の前に通常兵器による反撃力を強化することが先決であると回答されました。 ・植木千可子氏は、今のトランプ政権下では、三つの改正のうち、核保有の問題を除き、憲法改正も安保条約改正もあまり効果はないのではないかとの意見を述べられました。 ・北井邦亮氏は、日本国憲法の精神は非常に気高くていいと思っていますが、第9条の改正は必要です。核武装は私自身反対ですが、先程申しましたよう核のレイテンシー(日本が核武装するかもしれないよ)という抑止は必要であると返答されました。
その後、フロアの参加者も加わり、相互の間に活発なディスカッションを実施し、16時55分徳地秀士副理事長の閉会の挨拶をもって、(第9回)研究会は閉会しました。
閉会の挨拶 徳地秀士(猪木正道賞基金副理事長) 〔(第9回)猪木正道記念・安全保障研究会の記録は、年報『平和と安全保障』第12号に掲載します。〕
|









 パネリスト
パネリスト パネリスト
パネリスト