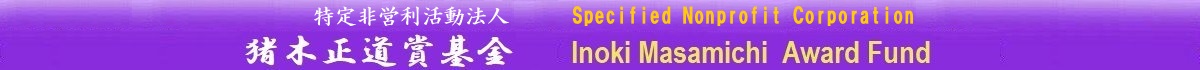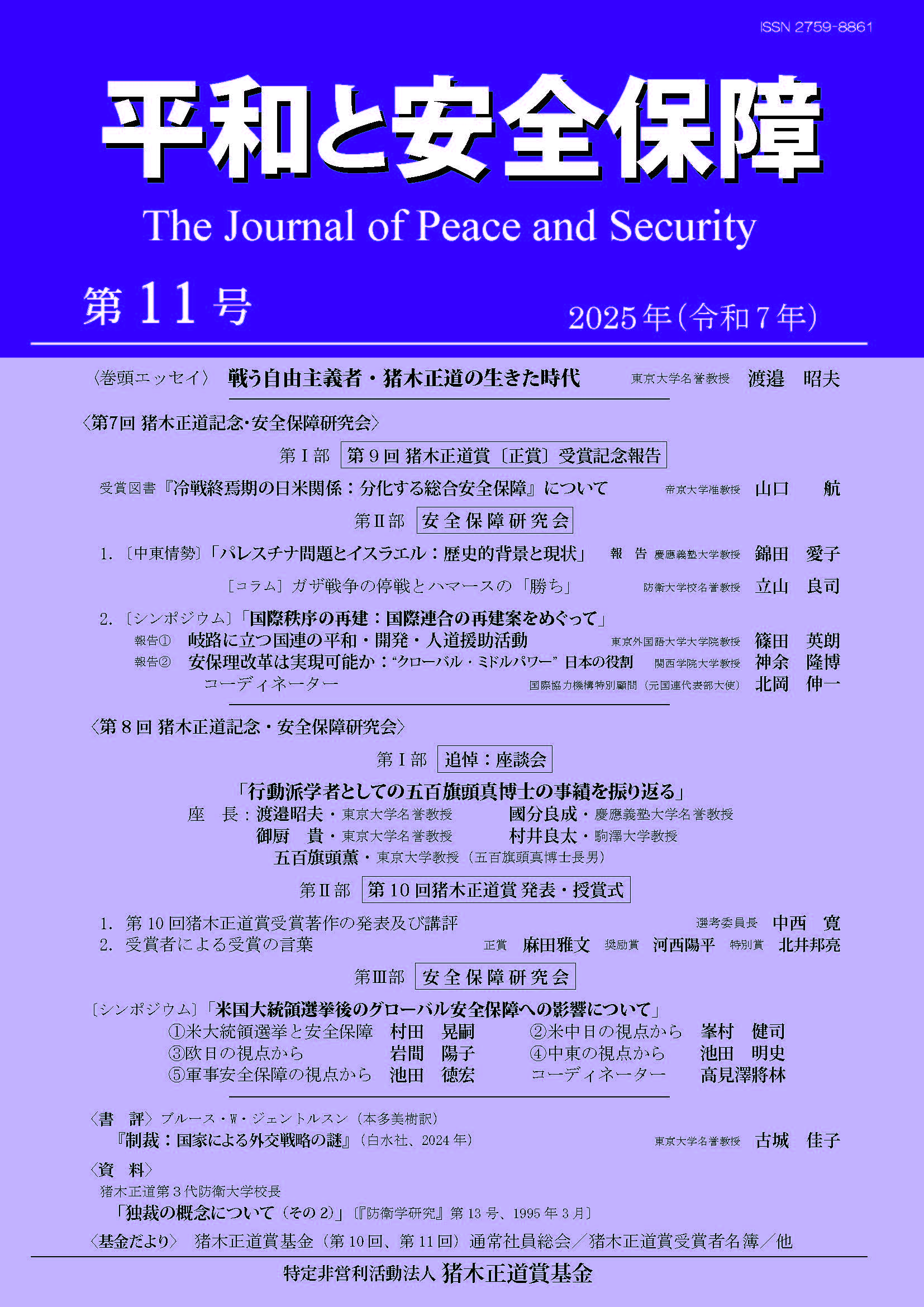第11回 猪木正道賞 発表・授賞式が挙行されました。
第11回猪木正道賞 発表・授賞式は、2025年11月16日(日)青山学院大学・総研ビル12階大会議室において開催した(第10回)猪木正道記念・安全保障研究会の第Ⅱ部において挙行しました。
Ⅰ. 選考委員会による第11回猪木正道賞〔正賞、特別賞〕の選考
(第11回)猪木正道賞選考委員会は、2025年11月11日(土)に国際文化会館において、赤木完爾(選考委員長)、尾上定正、庄司潤一郎、奈良岡聰智、村田晃嗣の各選考委員による最終選考(一部文書を含む)を行い、次の三著作を猪木正道賞〔正賞、特別賞〕に選考しました。
【正 賞】波多野澄雄 著
『日本終戦史1944-1945 ~ 和平工作から昭和天皇の「聖断」まで』
(中公新書、2025年7月25日)
【特別賞】 増田 剛 著
『次期戦闘機の政治史 ~ 選定過程にみる日米欧の攻防』
(千倉書房、2025年5月23日)
【特別賞】 大木 毅 著
『天才作戦家マンシュタイン ~「ドイツ国防軍最高の頭脳」―その限界』
(角川新書、2025年6月10日)
Ⅱ. 発表・授賞式
猪木正道記念・安全保障研究会第Ⅱ部における発表・授賞式では、総合司会の開会宣言に続き、赤木完爾選考委員長から第11回猪木正道賞著作の発表があり、選考経過と正賞、特別賞それぞれの著作に対する詳細な選評がなされました。
続いて赤木完爾選考委員長から3名の受賞者に表彰状と副賞が授与されました。
赤木完爾選考委員長 増田 剛氏 波多野澄雄氏 大木 毅氏 庄司潤一郎選考委員
Ⅲ. (第11回)猪木正道賞選考委員会による選評
令和7年11月16日
猪木正道賞選考委員会 委員長 赤木 完爾
選考委員会では、慎重審議の結果、正賞1点、特別賞2点を選んだ。選考理由は以下の通りである。
[正 賞] 波多野澄雄 著 『日本終戦史 1944-1945――和平工作から昭和天皇の「聖断」まで』(中央公論新社、2025年7月)
著者は、日本にとって先の大戦を四つの複合戦争と捉えている。すなわち日中戦争、太平洋における日米戦争、インド洋・東南アジアにおける日英戦争、最後の日ソ戦争の複合である。
本書は、1944年7月のマリアナ失陥から、1945年8月における日本の降伏決定に至る事情を詳細に跡づけ、最終的にこの四つの戦争が日米戦争に収斂して帰結する様を描いている。1944年秋以降、日本の軍事的敗勢は明らかであった。しかし軍事的敗勢と、降伏という日本政府の政治的意思決定は別の事柄であった。加えて戦前期日本の多元的な政治体制のもとでは、鈴木貫太郎首相は早期終戦を念頭におきつつも、徹底抗戦論の陸相、早期終戦論の海相を同時に閣内に抱えつつ、終戦に向けて迂遠な政治指導に腐心せざるを得ない事情が存在した。そこには「性急な終戦は陸軍の叛乱の危機を招き、戦争継続は国民の国体に対する離反を招く」というジレンマが存在した。
この間にあって、空襲と封鎖を含む戦況、徹底抗戦派の論理、本土決戦準備の実相、国内各グループの和平工作の動向、革新官僚の動向、陸海軍各々の省部の差異、米ソの動向などが克明に叙述され、1945年8月の二度の御聖断に至る事情が明らかにされている。
歴史叙述の常として、なされた決断は不可避のものと捉えられがちであり、別の道筋の可能性は顧みられないことが多いが、本書には懐の深い捉え方が提示されている。重厚にして周到な研究を踏まえた本書によって、日本終戦の経緯は80年の歳月を経て碑となった。本書に猪木正道賞(正賞)を授与する所以である。
[特別賞]増田 剛 著 『次期戦闘機の政治史――選定過程にみる日米欧の攻防』
(千倉書房、2025年5月)
国家の最高最先端の技術が結集されるのが、戦闘機開発である。したがってその開発は国家安全保障における最重要課題の一つでもある。しかもその開発は、軍事的要素のみならず、国際情勢、国内政治、さらには経済的利益が錯綜するなかで翻弄される。ながくNHK記者として外交・安全保障を取材してきた著者は、ことに航空自衛隊の次期戦闘機の選定をテーマとして2000年代前半から今日まで取材し報道してきた。
本書は「戦闘機と政治のかかわり」をテーマに、日米間のかけ引きや実務に携わった関係者の判断等を網羅的にとりまとめた労作である。戦闘機開発はごく専門的で狭い領域の問題であるが、反面それは関係者と関係国の利害や関心を大きく映し出す鏡でもある。日本が熱望したものの断念したF-22の顛末や現在進行形の日英伊の国際共同開発「グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)」に至る経緯など、一般読者の関心を捉え、啓蒙する内容である。
本書では、20年を超える丁寧な取材に基づく事実関係が分かり易く整理されており、注釈や参考文献も付記され、資料的価値が高い。さらに現代戦で無人機の役割が急拡大しつつある現状において、今後、有人戦闘機と無人機の最適配分など、我が国の防衛政策にとって重要な課題を視野に入れるとき、本書はそうした課題を検討する端緒となることが期待される。すぐれた調査報道である。
[特別賞]大木 毅 著 『天才作戦家マンシュタイン 「ドイツ国防軍最高の頭脳」――その限界』(KADOKAWA、2025年6月)
本書は、グーデリアン、ロンメルに次ぐドイツ国防軍で「名将」とされた軍人を対象とした三部作の集大成であり、著者年来の関心を反映して、新書とはいえ約450ペイジに及ぶ大作となっている。
本書の特徴は、自己弁護の傾向が強い自伝や回想録に依拠していた、冷戦という時代状況を背景として政治的に作られたマンシュタインの「虚像」を、欧米における最新の研究成果をもとに著者自身の研究を踏まえつつ実証的に再検証している点にある。その結論は、マンシュタインは、天才的な作戦家であったものの、20世紀の総力戦の時代には通用せず、自ずと限界があったとするものである。だが、その限界を、個々の軍人の資質に帰するというよりも、ロンメル、グーデリアンと同様に、戦略面での不利を克服するために作戦の巧緻に頼らざるを得なかった、「持たざる国」ドイツにという所与の条件と関連付けて論じている点は、示唆に富む。
さらに人間マンシュタインを論じる際に無視し得ないかつ微妙な問題である、ヒトラーとの関係、さらにナチズムの人種主義に対する姿勢などについても、客観的かつ冷静に評価して、「(ドイツ)国防軍神話」を、マンシュタインを軸に解体した点でも意義は大きい。
以上の評価から、本書は日本における第二次世界大戦期のドイツ軍に関する研究として一つの到達点を示し、わが国における広い意味での平和・安全保障研究の発展に寄与した。
以上
(受賞者によるそれぞれの「受賞の言葉」は、年報『平和と安全保障』第12号に掲載します。)